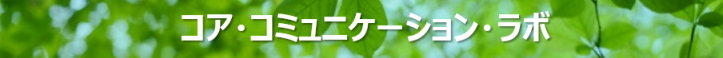諏訪大社を訪ねて

古代からの信仰にふれた時間
先週、友人たちとともに諏訪大社の4つの宮をめぐりました。
山梨県出身の私にとって、長野県の諏訪湖あたりは決して遠い存在ではなかったのですが、これまで訪ねたことはありませんでした。
諏訪大社は『古事記』の国譲り神話に登場する建御名方神(たけみなかたのかみ)が祭神とされ、出雲から諏訪へ移ったと伝えられています。
創建年代は不明なものの、すでに7世紀には確認されているので、日本で最も古い神社のひとつになると教えていただきました。
諏訪湖の南側に上社(上社)前宮(まえみや)・本宮(ほんみや)、北側に下社(しもしゃ)春宮(はるみや)・秋宮(あきみや)。
上社の中心的な宮である本宮は、戦国時代に武田信玄も戦勝祈願を行ったという武士の信仰を集めた宮。
前宮は、古代の祭祀の名残を残した厳かな印象。
春宮は春の訪れとともに神が宿るとされ、静かな境内が特徴。
秋宮は秋の収穫を祝う祭りが行われるためか、少し華やかな雰囲気。
それぞれの違いを感じてみるのも一興です。
で、特徴的なのが御柱(おんばしら)。
周辺の神社でも、社殿の四隅には必ず切り出された木が立てられていましたが、4つの宮では、さらに巨大な樅の木が神聖な境界を守っていました。
御柱は、神の依り代としての役割も持っているんだそうです。
諏訪の御柱祭(おんばしらさい)は7年に一度開催されるお祭り。
大木に多くの人が乗り、山から滑り落ちるようにふもとに向かう勇壮さは、他に例をみません。
開催のニュースだけではなく、事故の報道もよく目にするので、私も知っていました。
ホームページによれば、
御柱祭とは宝殿の造り替え、そして御柱を選び、山から曳き、境内に建てる一連の神事を指します。“御柱”となるのは樹齢150年、17メートルを優に超える選ばれた16本のモミの大木だけ。それを人の手で里に曳き出し、7年毎の寅と申の年に諏訪大社の社殿の四隅に建てます。その歴史は古く、室町時代の『諏訪大明神画詞』という文献には、「寅・申の干支に当社造営」が平安初期にすでにあったという記録が残されています。連綿と連なる御柱祭に諏訪地方の人々がかける思いは、現代でも非常に強いです。
ー 御柱祭ホームページより
平安時代以前から1200年以上も続くといわれる神事。
一体なぜこのような形になったのか…そんな疑問も湧いてきますが、地域が結束し、守ってきた精神が今も受け継がれていることに感動を覚えます。
新緑があふれる諏訪の自然の中で、ひととき歴史と信仰に思いを馳せた時間は貴重でした。
日本の中にもまだまだ知らない世界がたくさんありますね。
これからも足を延ばして、いろいろな体験ができたらいいなと思っています。
(2025年5月25日 岩田)