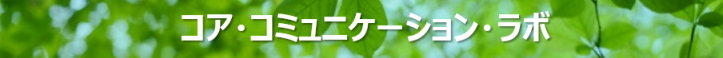アドラー心理学の入り口

読書会は格好の機会
今日は対面での読書会でした。
前回まではユング心理学入門でしたが、今回からはアドラー心理学入門です。
2013年発行の『嫌われる勇気』のベストセラーによって、日本でも一気にアドラー心理学への関心が高まったように感じます。
私自身はこれまでユング心理学関連の本ばかり読んでいたので、アドラー心理学がどのようなものか、ほとんど知らない状態でした。
この機会に学べるのも何かのご縁。
アドラー自身についても興味が湧きました。
アドラーは当初開業医でしたが、朝から夜遅くまで診察と勉学に励み、さらに夜は友人たちと議論するためにカフェに出かけたため、家にいることはあまりなかったそうです。
4人の子どもの育児は妻に任せきりだったと書かれています。
ロシアの才媛だった妻ライサはアドラー自身のグループの会合では秘書を務め、議論に参加するなどしたこともあるようですが、育児に忙殺され、そうした活動から離れたとか。
今日の参加者のひとりは、19世紀から20世紀にかけてのヨーロッパでも、女性は家という役割が固定されていたらしいことに注目していました。
一方で現代では女性も何かしら仕事を持つことが望まれ、専業主婦という言葉が死語に近くなっていたり、何も生産していない存在と扱われることもあるという話が出てきました。
立場によって、ちょっとした文章の中でも着目するポイントがいろいろあるものです。
実際アドラーの妻はどんな気持ちで家庭を守ったのでしょう?
ぜひ彼女について書かれたものがあれば読みたいという声もあがりました。
また、アドラー心理学では課題の分離を扱い、人生の課題は原則として本人が解決しなければならないと考えるとのこと。
「これは誰の課題か」という問いかけが必要になりますが、これは難問ですね。
出されていた例は、勉強が子どもの課題であるとすれば、いきなり「勉強しなさい」と親が言うことは、子どもの課題に踏み込んだことになるというものです。
とはいえ、現実には課題が入り組んでいて、誰の課題か分離することは簡単ではなさそうです。
さらには、仮に課題を丁寧に分けたとしても、相手の課題だからと、踏み込みたい自分に自制をかけるのは大変だという声も上がりました。
わかっていても動いてしまう人に、アドラーはどのように接したのか?
もう少しいろいろ調べてみたいと思いました。
何にせよ、新しいことをみなさんと一緒に学びつつ、経験や身近な例などをシェアし合う時間は毎回貴重です。
(2025年5月18日 岩田)