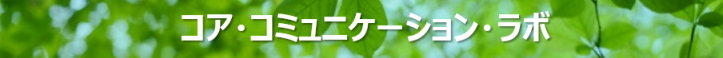自分ファーストがうまくいかない理由

宇宙の原理と縁起論
今日はオンライン読書会でした。
安岡正篤の人間学をテーマにした本を読んでいますが、そこから思いついたことを自由に話す場になっています。
このところの社会情勢から、自分ファーストについての話になりました。
つまり、自分さえ良ければいいという考え方ですね。
もちろん私たちはほとんど自分を一番大事にしています。
が、同時に他者の目を気にしたり、他者の気持ちを慮ったりもします。
それによって全体の中で自分のふるまい方を考えたり、場合によっては自分よりも他者を優先しようとすることもあります。
人間は社会的な動物であると言われますが、自分ファーストの人は他者から嫌われやすく、生存に不利になりやすかったことも起因しているのでしょう。
一方で、集団の中心人物としてその集団を第一に考え守ろうとしたら、集団内では尊敬されます。
自分たちのことを考えてくれる人になるからです。
では他の集団との関係ではどうでしょうか?
仮に全部で10の集団があったとして、その中のひとつが自分ファーストを高らかに宣言したら、他の9つは対抗しようとするでしょう。
9つの中のいくつかがまとまっていくこともあります。
本当はうまく分け合えば10の集団が平和に共存していく道があるのに、それぞれが自分だけのことを考えると奪い合いが始まります。
今日の読書会の参加者で量子力学に詳しい方が、自己中心とは宇宙の原理に反しているとおっしゃっていました。
私たちは個々が有機的に網目のようにつながっている存在だといいます。
だから自分だけ抜きん出ようとしても、突き抜けた分だけ揺り戻しがあり、反動で同じだけ下がってしまうのだそうです。
自分が良い方向に進もうと思ったら、みんなと一緒に良くなる方法を模索するしかない、長い間前提となっていたニュートンの古典力学の因果律は、量子力学の発展とともに光を失いつつあるのだ、と。
量子力学は仏教の縁起(えんぎ)の考え方に通じるものがあるというお話も興味深いところでした。
いまAIの進化など、時代が変化するスピードに圧倒されそうになっている私たちですが、宇宙の理は古くから発見されていたのですね。
人類にとっては、自分を大事にしつつ他者と共存していく道を模索するというのが、残された道なのかもしれないと思った時間でした。
(2025年4月6日 岩田)