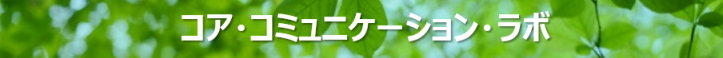日本人と桜

桜の開花が話題になる季節になりました
しばらく寒の戻りがあったかと思えば、昨日からは急に暖かくなりました。
春といえば桜、ですね。
桜の花が咲く時期は、ちょうど年度の変わり目ということもあって、卒業入学などの思い出に結びついています。
新しい門出のタイミングで、これまでの日常が失われる寂しさと、新生活への期待を同時に抱えるような季節です。
わずかな期間に花を咲かせ散っていくソメイヨシノは、淡いピンクの色合いとともに、そうした日本人の心象にしっかりと根づいているようです。
一方でニュースでは満開の桜の下で多くの人がシートを広げ、お花見をしている様子が映し出されます。
こういう風習はいつからなのでしょう?
調べてわかったお花見の歴史
お花見の始まりは奈良時代のようです。
が、当時は中国の影響で貴族の間では「梅見」が主流だったとか。
桜の花見が広まったのが平安時代で、特に中期以降は貴族の間でも梅より桜ということになったようです。
そういえば『枕草子』にも桜の美しさが描かれていたような…。
庶民に広がったのは江戸時代で、徳川吉宗が江戸の各所に桜を植樹し、庶民にも花見を楽しませるきっかけをつくったというのは初めて知りました。
隅田川の桜も吉宗が植えさせたものだったのですね。
豊臣秀吉と桜
お花見といえば、私でも知っているのが豊臣秀吉の醍醐の花見です。
1598月3月15日、京都の醍醐寺での盛大な花見は、彼の人生の集大成となるイベントでした。
このために醍醐寺の山の一面に約700本の桜の木を植樹し、金箔を施した御殿を建て、豪華な調度品を揃えたといわれています。
1300人を招いた豪華絢爛な宴で、秀吉は自ら茶も点てたそうです。
同じ年、秀吉はこの世を去りました。
農民の子として生まれながら、足軽として信長に仕えたことから彼のサクセスストーリーはスタートしました。
数々の戦功をあげたことで羽柴を名乗った後、本能寺の変を経て、関白に任ぜられ、武士として初めて朝廷から豊臣姓を賜り、天下統一を果たすというドラマチックな人生です。
最後は太閤を名乗り、満61歳の生涯を閉じました。
48歳で亡くなった信長に比べ、十分に生きたといえるかもしれません。
とはいえ、自らの死が近いことを予感しての醍醐の花見で、秀吉はどんな気持ちだったのでしょう。
彼の辞世の句は
「露と落ち 露と消えにし 我が身かな 浪花の事は 夢のまた夢」だそうです。(調べてみるまで知りませんでした…)
死の間際、徳川家康を含む五大老に、豊臣家を託しましたが、それは結局叶えられませんでした。
咲き誇る花もほどなく散ってしまうという「はかなさ」。
秀吉は自らの生涯と桜を重ね合わせたのかもしれません。
それはまた千年以上桜を特別なものとして愛でてきた日本人のDNAに刻まれているようにも感じます。
私も4月初めにお花見にいく予定です。(外で宴会をするわけではありませんけど)
世の無常、そして日本人の歴史、今年はそんなことを味わってみようと思っています。
(2025年3月23日 岩田)