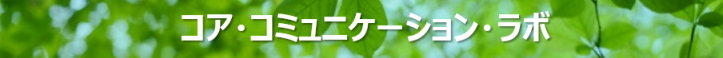祖法に従う是非

新しいものを取り入れることは簡単ではない
今日の読書会は『真・日本の歴史』(井沢元彦著)の最終回でした。
第8章では、江戸末期、幕府がオランダから開国勧告を受けた際に断ったいきさつについて書かれていました。
老中4名の連名での回答書には、拒絶する理由として「祖法」という言葉があげられています。
「祖法」とは、文字通り「先祖が定めたルール」のこと。
江戸時代初期、徳川家康は幕府を長く存続させるためのモラルとなる考え方を中国から導入したといいます。
それが忠孝を重んじる朱子学でした。
親孝行のみならず、先祖を敬う姿勢は、先祖の決めたことも守っていこうとする姿勢です。
鎖国も祖法であり、いくら当時のオランダが丁寧に開国の利を説いたとしても、決して受け入れることのできないことでした。
祖法という言葉は初めて聞きましたが、同じようなことは日常で頻繁に起こっていますね。
あるテレビ番組を観ていたら、時間のかかる発酵・熟成を画期的に短縮する新技術を開発したものの、伝統的な食品の生産現場に売り込みにいくと、けんもほろろに断られたと語っていた人がいました。
いくら素晴らしいものだと言われても、慣れ親しんだやり方を捨てることを決断できる人は多くありません。
国や社会、企業という大きな枠の中にもさまざまな祖法が存在しているでしょうし、個人の中にも無意識の祖法がたくさんあるのでしょうね。
ある時代の終焉とともに、終止符が打たれた祖法もたくさんあったことでしょう。
本の中では、明治維新後の日本に変革をもたらした立役者として、吉田松陰と渋沢栄一があげられていました。
前者は、天皇を絶対者とし、その他の国民は平等であるという考え方を広め、民主主義が育つ土壌を育てたという理由で。
後者は朱子学そのものは否定せず、孔子の教えに回帰することで士農工商という歪んだ価値観からの脱却を図り、資本主義を定着させる土台となったという理由で。
時代の転換期にはよくこうした人物が輩出されますね。
何ごとも長く続くことは祖法になり、ある時ほころびや弊害が目立ってくることがあります。
今や民主主義も資本主義も例外ではありません。
最近さまざまな情報から感じることは、多くの人が祖法を新たな視点で見直し、よりよい未来を模索しているということです。
今欲しいものは、守るべきものと捨てるべきものを分けることのできる知恵かな、と個人的に思った一日でした。
(2024年12月15日 岩田)