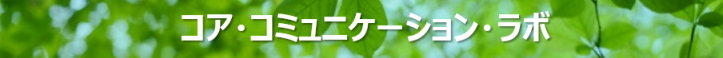インキュベーション効果

脳が自然に答えを出す仕組み
リカレントの学生としての私は、毎週授業の課題に取り組んでいます。
先週の後半も、「何を書こうか?」と考えつつ、なかなか書くことが思いつかず、つい先延ばししていました。
書く分量は少なくても、ポイントが絞れないと文章にすることは難しいものです。
とりあえず金曜日の夜に課題の問いを眺め、少しだけワードに打ち込みました。
ただ全く進めなかったので、そのまま放っておくことにしました。
この2年ほど夜10時以降はパソコンから離れ、部屋を暗めにして眠気を誘う本を読むというルーティンが定着しているので、夜の作業ではなかなか頭が働かないためです。
おかげで朝は早めに目が覚めるようになりました。
で、土曜日の朝目覚めたとき、自然に書きたいことが浮かんできました。
6時にパソコンに向かい、15分ほどで課題を仕上げ、ネット上のスペースに入力しました。
「何を書こうか」と悩んでいるときは、早く答えを出さなければと自分を追い立てているような感覚でしたが、朝の作業では、すでに出ている答えをただ打ち込むだけという状態でした。
このような体験のことをインキュベーション効果と呼びます。
インキュベーションとは「孵化(ふか)」または「抱卵(ほうらん)」のこと。
親鳥が卵を温めてヒナをかえすことです。
グラハム・ワラスという心理学者は、創造性の4つの段階として、準備、インキュベーション、ひらめき、検証を挙げています。
私の場合、課題に何を書こうかと考えたことが準備になり、答えが見つからず寝かせていた時間がインキュベーション。
朝になって書くことがわかったというのがひらめきです。
インキュベーション効果を活用すると、無理やり答えをひねり出そうとするときに比べ、余計なエネルギーを使わずにすみます。
これには脳の「デフォルトモードネットワーク(DMN)」が中心的な役割を果たしているのだそうです。
DMNとは、意識的な課題に集中していない時に活性化する脳のネットワークで、休息状態でも活発に働き、記憶の統合や無意識的な問題解決を行っているのだとか。
そういえば青砥瑞人さんの『BRAIN DRIVEN (ブレインドリブン) 』という本にもそのプロセスが詳しく書かれていました。(悲しいかな、私の記憶力では詳しいことは覚えられていないのですが)
ところで脳に答えを出してもらうために大事なことは何でしょうか?
それは「問い」の設定だと思っています。
「課題、なに書こう?」よりは、
「プレゼンテーションの中で最も心に残ったことは何だろう?」
「今後アフリカが発展していくために、日本ができる貢献とはなんだろう?」
などの方が具体的です。
具体化すればするほど答えは出しやすくなりますが、テーマによって抽象度を調整していくことも必要でしょう。
混乱させることなく脳に働いてもらうための問いを設定したら、あとは脳に任せてみる。
そして、出てきたアイデアを検証してアウトプットする。
このサイクルがうまく回っていったら、私たちの日々のストレスも減っていくのかもしれませんね。
(2025年6月22日 岩田)