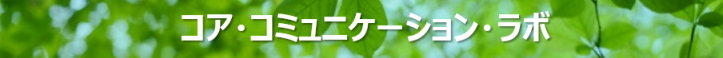人は考える存在

答えの出ない問いに向き合ってみる
「人間はただの葦にすぎない、この自然の中で最も弱いものである。しかし、それは考える葦である」
と記したのは、17世紀の哲学者パスカルです。
そう、人は考え、考えたことを言葉にしてきました。
哲学者と呼ばれる人たちは、考える専門家です。
科学なら立てた問いに対して、観察や実験などで答えが得られることも多いのでしょう。
逆に哲学の問いは、永遠に答えが見つからないものも多い。
答えの出ない時間に耐える精神力がなければ、とても哲学者にはなれないですよね。
最近ではタイムパフォーマンスが重視され、わからないことがあればすぐにAIに尋ねることが当たり前になってきています。
そんな中、時間をかけて熟考するのは苦痛ですらあります。
こんな時代だからこそ、あえて哲学者に近づいてみるのもバランスを取るために価値があるのかもしれません。

最近読んだ白鳥春彦さんの『哲学者たちが考えた100の仮説』には、多くの哲学者たちの熟考の末の仮説が紹介されていました。
(写真:図書館のコードを消しゴムマジックで消した箇所がちょっと不自然です(^^; )
パート1からパート7まであり、それぞれ「快楽・幸福・功利についてのさまざまな仮説」、「世界とはどういうものかについての仮説」、「自分の知見や知識が揺らいでくる仮説」などのタイトルがつけられています。
各仮説の前に「問い」が立てられていて、気になるものを自分で考えてみるのも一興です。
私が気になったのは、16世紀に『エセー』を著したモンテーニュについてのところ。
問いは、
「昨日の自分」と「今日の自分」は同じなのか?
昨日の自分と今日の自分が違うのではないかと考える人はほとんどいないでしょう。
なんとなく過去から現在の自分は同じだと信じて生きています。
が、そんなことも哲学者の思考では疑いの対象になるのですね。
モンテーニュは、「相反する事柄を愛したり、嫌ったり、誉めたり、けなしたりするのはなぜだろう」と考え、だから人間は絶えず変化しているのだという結論を導きました。
確かに昨日の自分と今日の自分が同じであるという証明はできません。
自然が常に変化しているように、人間も変化している。
記憶の中にはさまざまなものが保存されていますが、思い出すたびに微妙な違いが生まれていることもあります。
「自分」という意識が連続しているため、昨日の自分と今日の自分に変化がないと思い込んでいるだけなのかもしれません。
「自分」とは何で、どのように変化しているのか?
それも答えの出ない問いですが、昨日と今日の自分が違うことを前提にすると、軽やかな感覚になる気がします。
時には答えの出ない問いにも目を向けたいものだと思いました。
(2025年2月9日 岩田)