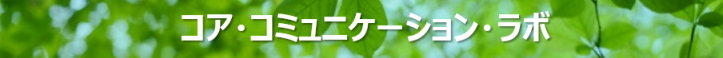「イデオモーター効果」とは?

行動や感情は思いがけない影響を受けている…
最近のニュースの大半は新型コロナウィルス関連です。
深刻な事態ですから当然のことであり、必要なことです。
何より情報があるというのはありがたいこと。
ただ正直なところ、多くの報道や人々のコメントに接しているうちに、疲れてきている自分がいて、現実逃避のようにYouTubeでお気に入り動画を観たり、軽く読める小説に走っています。
まぁ、それも仕方ないかなぁと、今は自分を甘やかしているところです。
あんまりいろんなことを抑圧すると却ってよくないですからね…。
(時々、本業を忘れるほどにストレス解消している自分はどうなのかというツッコミもあるんですが…)
私は映画やドラマより、自分でペースを調節できる小説のようなものの方がいいので、笑える小説が特にお気に入りです。
一気に気分が明るくなります。
家族に聞こえないよう、声を殺して笑っているという不自然な状態ではありますが…。
誰もいない時に、大きな声で笑えたらきっともっとストレス解消になるんでしょうね。
誰はばかることなく、笑えたらさらにいいなとは思いますが、しのび笑いであっても笑いの効果はなかなかのものです。
プライミング効果の話
さて最近、ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンの『ファスト&スロー』を読み返しています。
読み返すといっても、読んだことをほとんど忘れている状態なので、初めて読むような新鮮さです。
で、昨日の夜読んだ箇所が「プライミング効果」に関するところでした。
プライミング効果とは、(意識するかしないかにかかわらず)ある観念が頭にあると、それに関連した概念や言葉が想起されたり、行動や感情が影響を受けるというものです。
本の中では、「食べる」という単語を見たり聞いたりした後に、単語の穴埋め問題で「SO□P」が出たら、「SOAP(石鹸)」より「SOUP(スープ)」と答える確率が高まるという実験結果が紹介されています。
この場合のプライム(先行刺激)は「食べる」です。
もしプライムが「洗う」であったら、選ばれる単語は「SOAP」の確率が高くなるというわけです。
「イデオモーター効果」というのも、プライミング現象の一部。
プライムによって全く無意識に身体運動が発生することです。
ジョン・バルフという学者の実験では、高齢者を連想させるような単語を埋め込まれた文章を読んだ学生のグループは短文作成の課題を終えた後で別の部屋に移動する際、他のグループより明らかに歩く速度が遅かったと報告されているそうです。(もっと詳しく知りたい方は「フロリダ効果」で検索してください)
高齢者という言葉に影響され、自覚のないままゆっくり歩いていたということです。
よく考えてみれば私たちのまわりはプライムだらけですね。
見えたこと、聞こえたことすべてがプライムになりえて、それが知らず知らずのうちに自分の行動に影響を与えているのです。
まさに私たちの連想のネットワークのたまものといえます。
例えば、今このブログを読んでいるあなたにとっては、この文章すら何らかのプライムになりえるということです、ね。
(なるべく変なことを書かないようにします…)
連想のネットワークをよりよく利用したい
プライミング効果おそるべし、です。
さて、このイデオモーター効果、逆向きにも働くんだとか。
ドイツの大学で行われた実験のことが書かれていました。
部屋の中を通常の3分の1の速度で歩くことを指示された学生は、その後に問題を出されると「忘れっぽい」「年老いた」「孤独」など高齢者に関する単語を通常よりはるかにすばやく認識するようになったそうです。
つまり、ひとつ前の実験では高齢というプライムで行動が老人らしくなった。
後の実験では老人らしい行動で高齢という観念が強められた。
連想のネットワークは双方向ということです。
実際のところ、笑顔を作れば楽しくなるというのは本当です。
なので、イデオモーター効果を利用するのも賢いやり方でしょう。
笑ったら、気分もあがります。
ちょっと過剰な不安を抱え込んでいる自分に気づいたら、あえて笑顔になれる工夫をしてみるのもアリですね。
ということで、多少の現実逃避を自分に許すことにして、まずは自分の機嫌をとっていきたいと思っています。
自分の機嫌も接する誰かのプライムになるのですから。
(2020年4月19日 岩田)